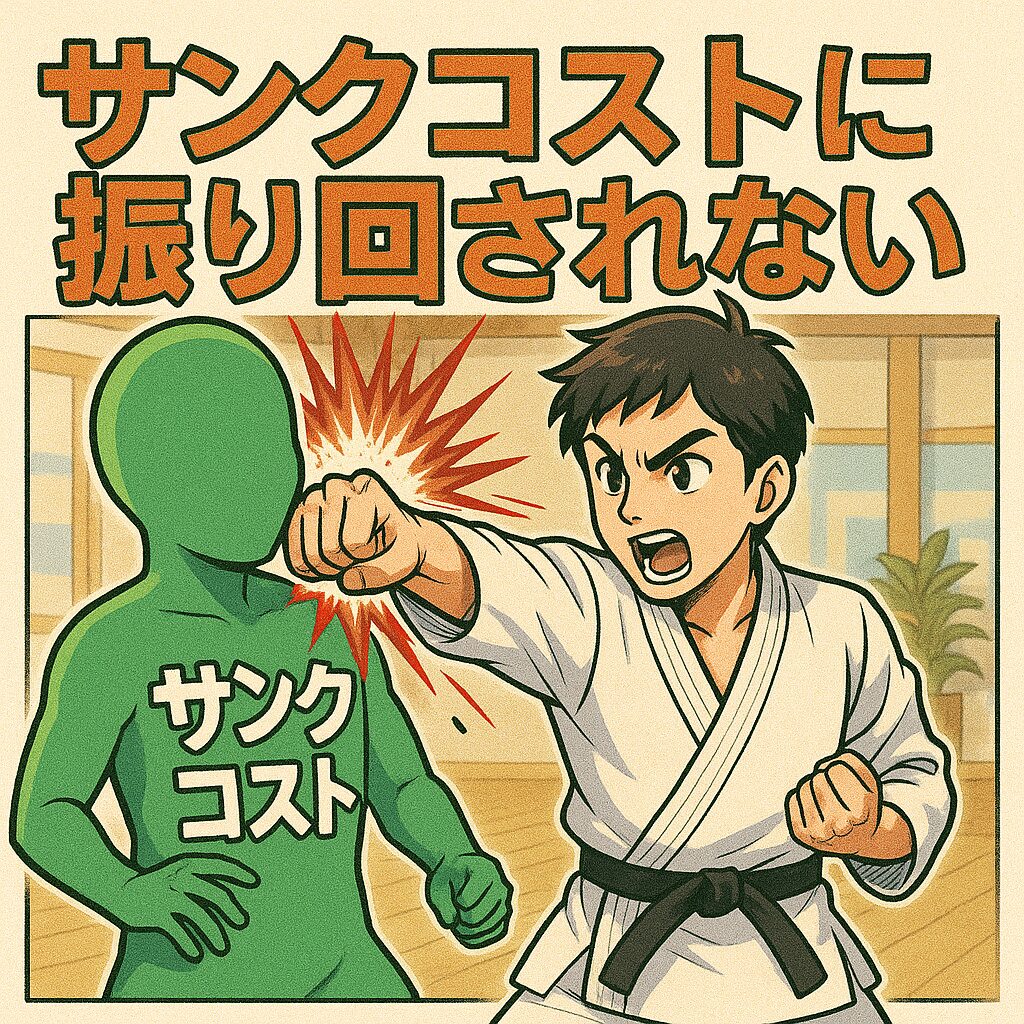経営をしていると、毎日のように決断を迫られます。
事業方針、人材配置、資金の投資先、商品開発の継続可否……一つひとつの判断が会社の未来を左右します。
理想は、常に合理的で冷静な判断を下すことです。
でも現実はそう簡単ではありません。
環境やその時の体調など、判断を曇らせる要因は無数にあります。
その中でも特に厄介なのが「サンクコスト(埋没費用)」です。
サンクコストには振り回されない経営をしたいものです。
スポンサーリンク
サンクコストとは何か?
サンクコストとは、すでに支払ってしまったお金や時間、労力など、取り戻すことができないコストのことを指します。
たとえば、3年かけて開発した新商品がまったく売れそうにないとき、多くの人は「ここまでやったんだから、あと少し頑張ろう」と考えてしまいます。
この「ここまでかけたコスト」がサンクコストです。
合理的に考えれば、「ここまでかけたコスト」は関係なく、「今後その商品にリソースを注ぎ続けるべきか?」という未来志向で判断するべきです。
しかし、過去の投資がもったいなくてやめられない。
それが人間の性(サガ)でありこの心理が、経営判断を狂わせます。
サンクコストの罠にハマるとどうなるか?
サンクコストの罠にハマると、次のような弊害があります。
-
赤字プロジェクトを切れない
-
成果の出ない人材に投資を続けてしまう
-
撤退すべき事業から手を引けない
こうした判断ミスは、「過去にかけたコスト」を軸にしてしまっていることが原因です。
それはつまり、「未来の損失を減らす」ことより、「過去の努力を正当化する」ことを優先してしまっている状態です。
スポンサーリンク
冷静に判断するために必要な意識
では、どうすればサンクコストに振り回されずにすむのでしょうか?
「過去」は切り離して考える訓練をする
意思決定は未来に向けたものです。
「今ここでゼロから始めるなら、それを選ぶか?」という視点を持つと、サンクコストの影響を受けにくくなります。
数値で判断する仕組みを作る
主観に頼ると「せっかくここまで…」という感情が入り込みます。
あらかじめ撤退基準や評価指標を設定し、感情ではなく、数字などで客観的に判断できる状態を整えておくことが大切です。
他者の視点を取り入れる
外部の視点は冷静さを取り戻す助けになります。
定期的に、信頼できる第三者と判断を共有し、思い込みをリセットする時間を持つことが有効です。
まとめ:正しい判断のために、あえて「捨てる」勇気を
経営とは、限られたリソースを「どこに、どう使うか」を決める連続です。
そのためには、「やめるべきものをやめる」判断も、極めて重要なスキルになります。
サンクコストに心を引っ張られたままでは、過去に縛られた経営になってしまいます。
未来を切り拓くためには、「引き返す勇気」も時には必要です。
スポンサーリンク